修士論文を書く
Table of Contents
1 はじめに—なぜ人類学か
- 旅行ぎらい(いまでもフィールドワーク直前は毎回登校拒否症)
- 「なんであなたのような旅行嫌いが・・・」
- 高校の時
- バタイユ、レヴィ=ストロース
- 「社会学」 構造主義
- 院進学の時
- 「長男がしっかりしているからいいよ」
- かつては院進学とは ふつうの 人生をあきらめることでした
- すなわち、修士から博士、学者という一本の道しか残されて いなかったのです
- 卒論で(たまたま)東インドネシアのティモール島を扱った
- 修論で東インドネシアのスンバ島を扱うこととした


2 東インドネシア
- Why Eastern Indonesia?
- (光ありき There is Light)
- 構造主義ありき There is structuralism
- 構造主義 → 親族論(『親族の基本構造』レヴィ=ス トロース)
- Structuralism → Theory of Kinship ( The Elementary Structure of Kinship by Claud Levi-Strauss)
- → 母方交差イトコ婚 が一つの問題でした
- — Matrilateral Cross Cousin Marriage
- 構造主義→ オランダ構造主義
- Structuralism <– Dutch Structuralism (on Indonesia)
- この二つが焦点を結ぶのがインドネシア東部だったの です
- The two streams meet at the Eastern part of Indonesia
2.1 親族組織
- 今日の講義の大きな物語は、母方交差イトコ婚に対す るわたしの理解がじょじょに(修論、 フィールドワーク、博論を通して)深まっていった描写を筋とし ています
- My story shall revolve around Matrilateral cross cousin marriage (MCCM hereafter) — how my understanding of this system deepened as I progressed from MA to Fieldwork and then to the dissertation writing
- この中に母方交差イトコ婚に興味がある人、もっと一 般的に言って親族組織に興味のある人はいないでしょ う
- I know nobody is interested in kinship
- わかってます
- 今日だけ「親族組織に、とりわけ母方交差イトコ婚に とっても興味があるふり」をしてください
- Let's pretend we're interested in
- actually, fascinated by
- Kinship in general and Matrilateral cross cousin marriage (MCCM) in particular
- まずは基礎編です
- Let's start from the basics of Kinship
2.2 父系制
- 母方交差イトコ婚の前に、簡単に「単系」(母系と父系)について述 べます
- Before proceeding to MCCM, let me talk about unilineality (patrilineality/matrilineality)
- 自分 (EGO) の系譜の辿り方、「先祖の選び方」の問 題です
- It's about how you [EGO] trace your descent and how to choose your ``ancestors''
- 図を見てください
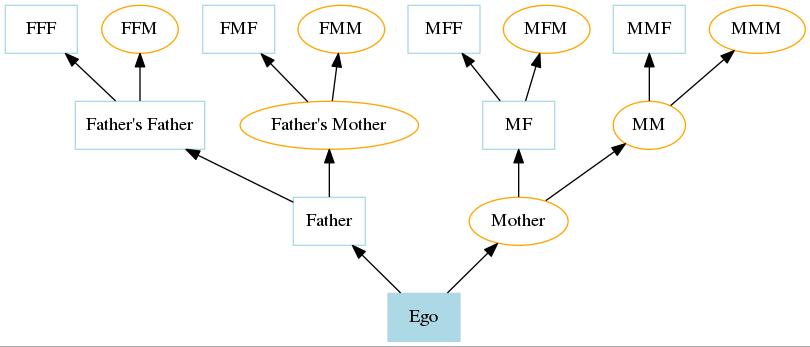
- 世代を遡る毎にどんどん「先祖」(の候補者)が増え ます
- The number of ancestors increases exponentially as you are going up the genealogy
- 父からのみの「先祖」を選ぶ仕方を「父系」といいま す
- You can, for example, choose your ancestor only via ``fathers'' — this way is called patrilineality
- 東インドネシアには母系の社会もたくさんありますが、 ここでは、父系に限定してお話しします
- 日本の名字の継承のシステムです
- 「社会が父系制」と言うとき
- 社会のほどんとの要素の継承が父系的に行なわれると いうことになります
- 世代深度は深く、記憶される名前は10世代に渡ること もあります
- People in Ende reckon their own genealogy up to 10 or more generations up
- そのような社会では父系の集団が基本になります
- Then the society will be divided into discrete patrilineal groups
- 中川家、川中家、中山家、山中家、といった父系集団 が、社会を構成する単位となります
- Those patrilineal groups, such as the Nakagawas, the Kawanakas and so on, are the building blocks of the society
- 図は一つの父系集団をあらわしています(矢印は親か ら子供にします)
- The next figure shows a patrilineal group (showing only men)
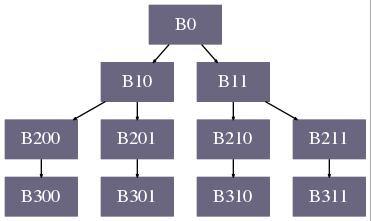
2.3 母方交叉イトコ婚
- Now about MCCM
- 「母方交差イトコ婚」とは(男が)母方の交差イトコ と結婚するシステムです
- A MCCM is a marriage where a man marries his matrilateral cross cousn
- Let me explain "matrilateral cross cousin"
- First about "Cross cousin"
- イトコとは親がキョウダイであるような二人の人間で す
- "Cousins" are those whose parents are siblings
- 図を見てください(矢印は親から子供にします)
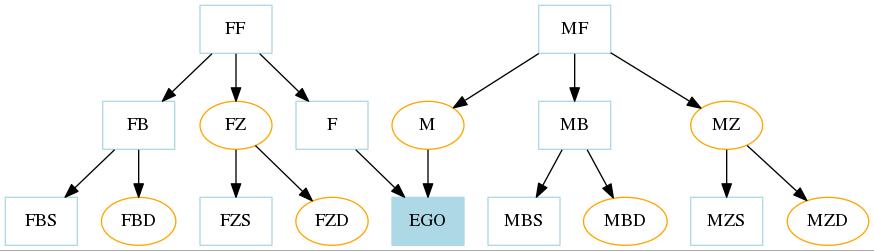
- F:父親、M:母親, B:兄弟、Z:姉妹、S:息子、D:娘、C:子供
- Now about "Cross cousin"
- (多くの社会では)平行イトコと交差イトコを区別 します
- In many societies, people differentiate two types of cousins: parallel and cross cousins
- 平行イトコとは親同士の性が同じ(男と男、女と女) ようなイトコ
- Parallel cousins are those whose parents are same sex siblings (like B/B or Z/Z)
- 交差イトコとは親同士の性が違う(男と女)イトコ のことを言います
- Cross cousins are those whose parents are siblings of different sexes
- 交差イトコと並行イトコを下の図(再掲)で探してください
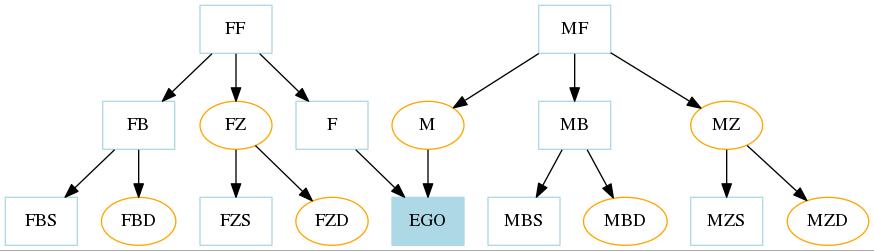
- すなわち母方交差イトコ婚とは:
- 男が母方の交差イトコ(母の兄弟の娘)と結婚する ことをいいます
- Thus a MCCM is a marriage with the cousin whose mother is your father's sister
- MCCM is a marriage where you marry with your MBD
- なんだかえらくややこしいいことをしている様に見え ますが、 It may sound unnecessarily complex
- じつはこの結婚が(理想的に)運ばれた場合、とても きれいな社会構造が生まれるのです
- 図を見て、確かめてください/B2 を自分として「母方交叉イトコ婚」を確認してく ださい
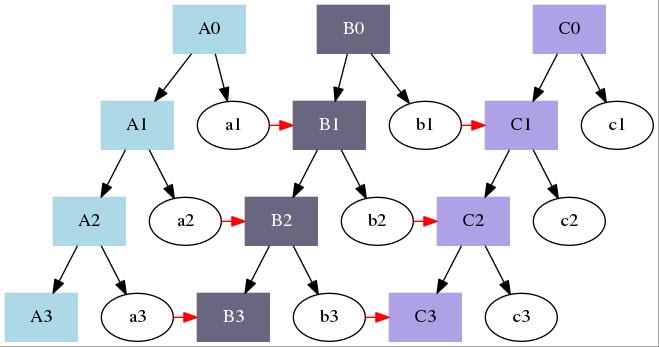
- A父系集団(A0、A1、A2・・・)、B父系集団、C父系 集団・・・があります
- A に生まれた女性(a1、a2、・・・)はBの男に嫁ぎま す
- B に生まれた女性(b1、b2、・・・)はC の男に嫁ぎ ます・・・
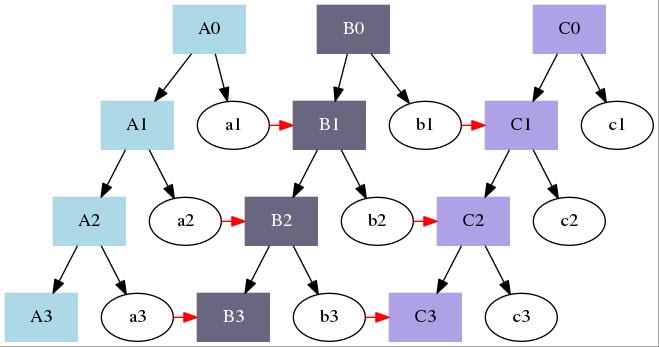
- 全体として、次の図のような「女性の移動」が見られ るのです
- これを非対称的縁組 (asymmetric alliance) と言い ます
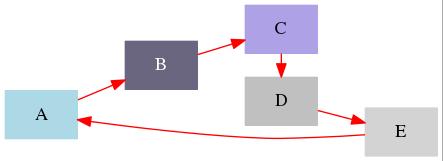
3 読み方
- かつては院進学とはふつうの人生をあきらめることでした
- すなわち、修士から博士、学者という道しか残されて いなかったのです(あとはバイト)
- わたしの文化人類学の大学院ではフィールドワークは 博士になってから、
- 修士時代はとにかく文献を読む、というのが慣例でし た
- わたしの修士時代はおそらく、人生の中でいちばん勉 強した時だと思います
- どうぞ、いっぱい勉強してください
3.1 勉強の仕方
- 精神論と技術論に分けてお話しします
- 精神論とは「どのような態度で本を読むべきか」とい うこと
- 技術論はもっと実践的なことです(詳細は次の講義)
- 精神論
- 批判的に読め
- — 理論的な本には難癖をつけよ
- 広汎に読め
- — 流行りの理論の生命は20年/理論は信頼するな
- 積極的に読め(難易度は高いです)
- — 受け身に読むのではなく、自分の「役」に立てる ように読む
- — 修論を書いている時によくわかるでしょう
- 技術論
- 技術論ではコンピューターの使い方について述べます
- コンピューターを使っての読書ノーツの取りかたも、
- フィールドの記録としてのコンピューターの使い方も ほぼ同じこととなりますので、
- フィールドワークの項で述べたいと思います
- コンピューターを使う上での基礎的なこと(すくなく とも私はそう思っている)をここで述べておきたいと 思います
- アドバイス: プレインテキストを使え
- ここ を開いてください(右クリック→新しいタブ/ CTRL-TAB/(終了したら)CTRL-W)
4 書き方
4.1 買うべき本
- 木下是雄 『理科系の作文技術』 (link to Amazon)
- 本多勝一 『日本語の作文』 (link to Amazon)
- 前者は 必読 です
- Fallacy に関する本はたくさんあると思います
- 木下先生の教え
- (わたし風にアレンジしています)
- 分かり易く書け → 論文は 取り扱い説明書 のように書きましょう
- へんに難しいコトバを使わない
- 知恵熱 にかかると、(自分で分からない ような)難しいコトバを使いたくなるものです
- Dilbert の教え
- こんな風に書きましょう
(^_-)

4.2 論文の書き方

- マトリョーシカ人形と大リーグ養成ギプスの2点あり ます
- まずはマトリョーシカ人形から
- One Sentence One Idea
- One Paragraph One Topic
- Topic Sentence
- 文 (sentence)
- 短かく!
- 複文は避ける
- 「雨が降っている が 中川せんせいが学校にきた」
- 「雨が降っている」「中川せんせいが学校にきた」
- 複文は、しばしば、論理が通っているような錯覚を与える
- One sentence one idea
- 「1043年に構造主義宣言とも言える論文の中でレヴィ =ストロースは・・・と主張した」→
- 「レヴィ=ストロースの・・・論文は構造主義の宣言である。その中で彼は・・・」
- 段落 (Paragraph)
- One paragraph one topic
- 段落の冒頭は topic sentence
- ハッキングの『表現と介入』からランダムに3つ連続 する段落を引用します
あらっぽく言えば、ニュートン=スミスの存在論的要素 と認識論的要素とが私のいう対象にかんする実在論を意 味することになる。二つの要素があるのだから、二種類 の反実在論が存在し得る。一つは (1) を拒否し、他は (3) を拒否する。(p.12)
存在論的要素を否定してもよかろう。 理論を文字通りに受け取らなければならない、という ことが否定されるのである。【略】
道具主義は (1) を否定する。そうる代わりに (3) を否定してもよかろう。 一例は【略】
- Topic sentence は「大事なことは先に書け」の段落 バージョンである
- 修論の主張は修論の冒頭に書く!
- 章の主張は章の冒頭に書く!
- 節の主張は節の冒頭に書く!
- 論文はマトリョーシカちゃんだ!

- つづいて「大リーグ養成ギプス」です
- 口語調のことば
- 「わけ」、「だから」、「それに」、「すごい」
- 意味不明を白状することば
- 「ばかり」、「ぐらい」、「かなり」、「など」、 「思う」、「思われる」、「だろう」、「であろう」
- 断言せよ!
- 断言できないなら書くな
- 余分な形容詞・副詞
- 「非常に」、「たいへん」、「とっても」
- 接続詞(らしきもの)
- 「...が」(接続詞としての「が」)、 「...と(接続詞としての「と」: 「−−すると」、「−−であると」)、 「・・・で」(接続詞としての), 「そして」、「また」、「つぎに」、「まず」、 「そこで」、「さて」、「ところで」、「ようする に」、「つまり」
- 「しかし」!
- 代名詞・指示代名詞(形容詞・副詞)
- 「これ」、「それ」、「あれ」、「この」、「その」、 「あの」、「ここで」、「そこで」
- 「もの」、「の」
- (「というもの」、「ということ」、「...のは」 という形で頻出する)
- 「こと」はなるべく使わないように。
- 「わけ」、
4.3 考えるための技術
- ひっくり返し論法(使いすぎに注意)
- 障害にもとづいて差別する → 差別が「障害」をつく る(社会構築論)
- 敵同士が戦争する → 戦争が敵をつくる(構造主義)
- おっちょこちょいだから失敗する → 失敗が「おっちょ こちょい」を作る(性格の反実在論)
- 繰り返しますが:使い過ぎに注意してください
5 とまぁこんな風にして
- とまぁこんな風にして
- 構造主義的な卒論そして修論を書きあげました
- パーソナルコンピューターはまだない頃でしたので、 手書きです
- 指導教官に原稿を渡した所
- 「いいんじゃない」というありがたいコメントをいた だきました
- これが指導です
- むかしは指導はいっさいありませんでしたから
- いまは指導があります
- 複数の先生に原稿を渡してコメントをもらいましょう
- (予定では)いま11時半ころ・・・かな?
- 第2講義 インドネシアでフィールドワークをする
- Back to Index