フィールドワーク
Table of Contents
1 はじめに
- エンデってどんなところ?
- なぜ東インドネシアだったのか?
- インドネシア語がはなせるまで
- エンデ語がはなせるまで
- フィールドノートの取りかた
- コンピューターの使い方(その2)
2 日本からジャカルタへ
- 「フィールドワークは2年」が慣習の時代でした
- (1970年代)フィールドワークに行くと「終わるまで帰っ てこれない」状況でした
- 「泣いて帰ってくるなよな」と先生に言われました
- 帰ってくれば、それで人類学者への道は閉ざされる、 そんな時代の話ではあります
2.1 ジャカルタへ
- 1978年度の奨学金をとったものの
- インドネシアからの調査ビザがなかなか出ません
- ぎりぎり待ったのですが、しようがないので学生ビザ で 1979-03-27 にインドネシアへ飛びました
- 数ヶ月ジャカルタで下宿をしていました
- アドバイス: (中根先生)大使館とは 付かず 離れ ず
- その間、インドネシア大学 の学生になり、インドネシア語の授業に出席しました
2.2 インドネシア語を学ぶ
- 新しい語学を学ぶ時の一つのテクニック
- 「一日100(いくつだったか・・・)の新しい単語」
- 本や新聞を読むときに必ず知らない単語をノート(単語帳)に書き出す
- ノルマは一日100語
- 最初はすぐに終わる(ほとんどが知らない単語だから)
- 一度書いた単語をもう一度書き込む時はくやしい
- そして1ヶ月もたつと・・・
- 「100語」がつらくなってくる/「知らない単語」が 少なくなる
- ある日、下宿先のお手伝いさんと話せるようになった
- 語学の学習ではそういう瞬間があるのだと思う
2.3 フォックス先生との連絡
- この頃は東インドネシアの人類学調査ははじまってまもない頃 でした
- 「東インドネシアの人類学」と言えばオーストラリア 国立大学(以後 ANU)のジェームズ・フォックス教授 が中心です
- ジャカルタにいる間、彼と手紙のやりとりをして、フ ローレス島のエンデという地域を調査地として決めま した
- アドバイス: 海外とコネを作ろう
3 いざフィールドへ!
- インドネシア科学局(調査許可を出すところ)と移民 局を何度もたずね、
- やっとやっと調査許可(と調査ビザ)を手に入れまし た
- アドバイス: 調査許可はちゃんと取りましょう!
- いよいよ出発です
3.1 縁を辿って
- 日本の大学でのインドネシアからの同級生
- 彼女の知り合いのフローレス人@ジョグジャカルタ、 ハンス先生
- ハンス先生の紹介状:エンデの町のモンテイロさん
- モンテイロさんが町の「村人」を紹介してくれる
- 町のキリスト教の教育オフィス、アドルフスさんの村へ
- (与太話)首狩り
3.2 エンデってどこ?
- (左)インドネシアの中のNTT州の位置です
- (右)NTT州の中でのフローレス島の位置です


3.3 「エンデ」が指すモノ
- エンデ県 (Kabupaten Ende/Propinsi Nusa Tenggara Timu)
- エンデの町(エンデ県の県庁所在地)
- エンデ島(エンデ人のかつての中心地、エンデの町か ら見える)
- エンデ語(エンデ県には他にリオ語、ンガオ語がある)
- エンデ人(エンデ語を喋る人たち)
- 最も広義:エンデ県あたりに住む人たち
- 最も狭義:(山岳部から見て)海岸部の(イスラム の)人たち

- 一つの島にいくつもの言語が喋られています(五から十)
- 方言ではありません
- エンデ県で喋られている言葉は三つあります
- この三つは方言と言語の間くらいの違い
- 西からンガオ語、エンデ語(ジャッオ)、リオ語(アク) と呼ばれます
| Nga'o | Ende | Lio | Indonesian | |
|---|---|---|---|---|
| I | nga'o | ja'o | aku | saya/aku |
| they | imu ko'o | ebe | ebe | mereka |
| this | ke | na | ina | ini |
| hate | bhia | bharho | ngange | tidak mau |
| then | dheko lepo | nduu | nduu | kemudian |
| sit | ngodhu | ngambe | mera | duduk |
| Nga'o | Ende | Lio | Indonesian | |
|---|---|---|---|---|
| rain | urha | ura | uja | hujan |
| line | ula | ura | ura | garis |
| dog | dako | rhako | lako | anjin |
| sun | dela | rhera | leja | matahari |
| south | dau | rhau | lau | selatan |
| year | liwa | xiwa | kiwa | tahun |
| run | palu | paru | paru | lari |
3.4 エンデの町ってどんなところ
- エンデの町は海のそばです
- フローレス島最大の町です(たぶん人口5万人ほど)









3.5 エンデの村ってどんなところ?
- エンデの町から西へ20 kmほど乗合バスで旅します
- 道は海岸沿いです
- 車から降りて、5 kmほど山を上るとわたしの村に到着 します
- 古い写真からお見せします。



4 楽しい日々
- 最初の2・3ヶ月は積極的に情報を集めまわります
- What a Wonderful World (Slide Show 02:27) といいたくなるよ うな状況です
- この2・3ヶ月で論文が何本も書けるような情報がいっ ぱいありました
- 博論さえもすぐ書けそうでした
- こんな格好してフィールドワークしてます

4.1 親族名称
- たとえば母方交叉イトコ婚についてはすぐに沢山の資 料が集まりました
- とくに親族名称については驚くほどの体系的であるこ とがわかりました
- さきほどの図を使って説明します
覚えてますか? ここで B2 を EGO と考えましょう
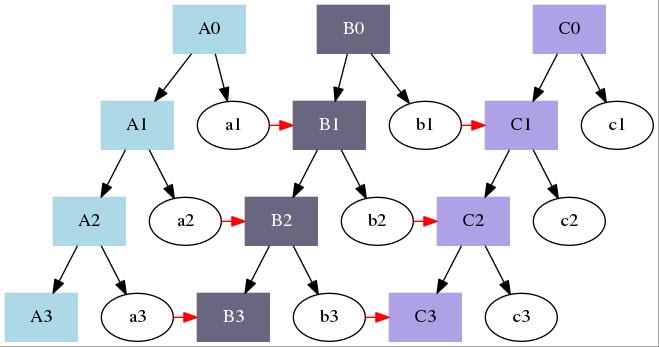
- 説明しやすくするためにさらに一世代上に足します。
- その上で、具体的にインフォーマントとのやり取りを お話しします
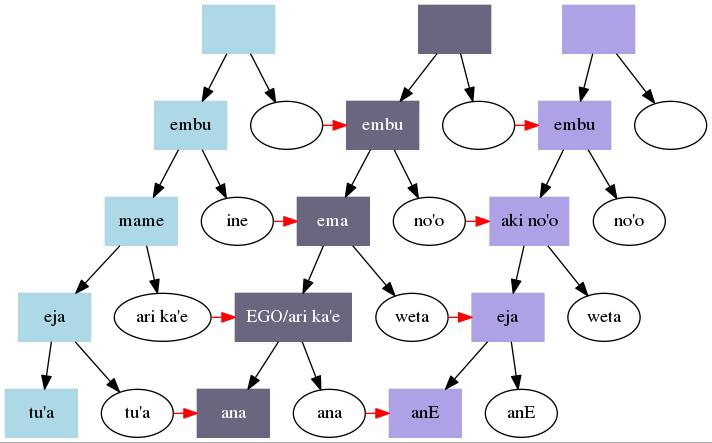
4.2 非対称的縁組
- そして下の再掲図通りに次のような縁組 (alliance) が出きあがり ます
- Β を EGO のグループとすると、
- A がワイフギバー(嫁を与える者)となり、カッ エウンブと呼ばれています
- そして C がワイフ・テイカー(嫁を受け取る者)で、 ウェタアネと呼ばれます
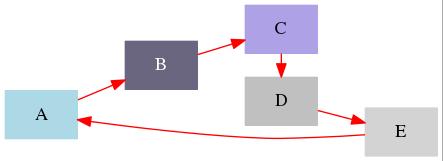
4.3 贈り物交換
- この関係に基づいて贈り物交換が行なわれます
- カッエウンブ(嫁を与える者)からは豚、布、米、バナ ナなどなどが贈られ
- ウェタアネ(嫁を受け取る者)からは象牙、金細工、 (豚以外の)動物、お金などが贈られるのです
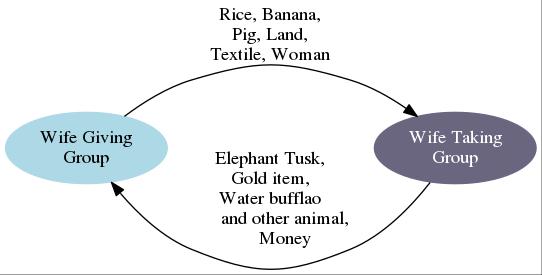





4.4 エンデ語
- エンデ語に辞書はありません
- ぶっつけ本番で習うしかありません
- 村には数人インドネシア語が流暢な人がいます(小学 校の先生など)
- とは言えわたしのインドネシア語はまだ流暢とは言え ず、村ではかなり苦労しました
- 言葉も覚え、フィールドワークも順調、楽しい日々で した
- What Game Shall We Play? (Slide Show 04:29)
5 混沌の日々
- 数ヶ月たち、村人の顔と名前もわかり、その親族関係 もなんとなく分かるようになり
- インタビューだけでなく、いろんな出来事を詳細に記 録できるようになると・・・
- 聞いた話と見た話が全然違うことがわかるようになり ました
- 村の風景 (Slide Show 07:01) (出だしだけプレイする)
5.1 おじさんのぶつくさ
- わたしは短期間の調査は信用しません
- 短期間の聞き取りだけの調査からは、明瞭な構造がす ぐ見てとれます
- しかし、じっさいに活動に参与すると構造からの ずれ が 見えてきます
5.2 「近頃のわかものは・・・」談義
- 簡単に行ったり来たりできるのはうらやましい
- ただし、「いつでも帰るつもり」でフィールドワーク をしており、じっさいすぐに帰ってきる
- 「あ・あれが足りない」といって、また出掛ける
- 結果:博論を書けない
- アドバイス: 「これが最後のフィールドワーク」 「帰ったらおしまい」と思ってフィールドワークをし ましょう
- 短いフィールドワークを何度しても、それ は長期フィールドワークにはかないません
5.3 イデオロギーと実践
- 第一に母方交叉イトコ婚はほとんど行なわれません (数え方によるのですが5%ほど)
- 記憶されている系譜の深度が深いことから、ある二人 の関係をきちんと特定できないのです
- ある人は、わたしの母の父の系譜を見てい くと、嫁を与える者になるのに
- 父の父の母の父の側の系譜を辿ると嫁を受け取る者に なってしまう
- そんな状況が氾濫しているのです
- エンデの村で適当に二人をとれば
- 二人の関係はつぎのどれかになります
- 姻戚関係、すなわち:WG/WT あるいは WT/WG
- 血縁関係は AG/AG (Agnates 血縁者より)とあらわ します
- めったにないことですが、可能性としては「赤の他人」 (これを NR/NR Non-relative とあらわしましょう) ということもあるかもしれません
- 具体的には市場(いちば)で出会う人がそれです
- 以上が理想(イデオロギー)の状況です
- じっさいは、世代深度が深いこと、そして
- 母方交差イトコ婚はほとんど行なわれていないことか ら
- (誇張して言えば)次の図のようになります
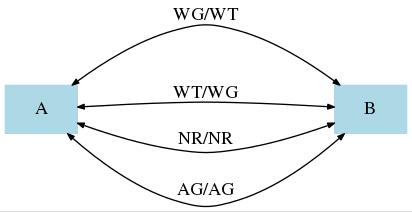
5.4 たとえば葬式
- それにもかかわらず、日々の生活(すべて親族関係が しきっています)はすすんでいます
- 葬式や結婚式では親族関係にもとづいた贈り物が前面 に出てきます
- 「死者の父はおれのウェタアネ (WT) だ。だけどおれの嫁は 彼の親族集団の出身なので、カッエウンブ (WG) にもなる」
- わたし「どうするんだ?」
- 「二回行く」
- なんてこともしょっちゅうあります
- 葬式 (Slide Show 03:54)
5.5 鬱屈
- フィールドワークの時はだれでも鬱屈する時がありま す
- アドバイスはありません
- 「帰ったらおしまい」ですので簡単に帰れませんでし た
- 親から送ってもらった『文藝春秋』を表紙から裏表紙 までななめるように読みました
- 「あ!この広告、まだ読んでない!」
- イギリスから来た人類学の学生さんが「泣い て(フローレス島から)帰ってゆきました」
- 人間が嫌になる時がありました
- 蟻をみてました








5.6 お金
- もっとも気が重くなるのは「お金」に関するもろもろ の出来事です
- 「歴史」や「文化」に詳しい有名な人に話を聞くため に新しい村に行ったことがあります
- 「しゃべってもいいが、お金を払わなければいけない」 というのです
- ・・・
- 鬱屈
6 記録をとる
- できることは、ただただフィールドノーツをとってゆくこ とです
- より一般的に記録の取りかたについて少し語りましょ う
6.1 カメラ
- わたしの調査ではカメラはあまり重要ではありません
- (→ 映像人類学からの批判があるでしょう)
- 記録として写真を撮るにはコンデジあるいはスマート フォンについているカメラで十分でしょう(電源確保 の仕方に依存しますが)
- ただ、後日見て楽しいのは一眼レフで撮った写真です ボケが楽しいです


6.2 録音
- インタビューではかならずノーツを取りましょう
- 録音は飽くまで 補助 です
- ノートを取るのが面倒で、録音だけにすると、その記 録は残りません(断言します)
- 体調が悪いとか、その他の理由で録音だけになったと きにも、必ずすぐに(一週間とあけてはいけません) トランスクライブしておきましょう
- 対人のインタビュー以外では(たとえば会議とかでは) もちろん録音が必要です
- この場合も、一週間以上あければ、そのデータは消失 すると思っておいてください
6.3 野帳のすすめ
- フィールドにもっていく手帳をフィールドノートブッ ク、ここでは「フィールドノート」と呼びましょう
- ちなみにそこに書かれた内容を「フィールドノーツ」 と呼ぶことにします
- さて、フィールドノートは、 もちろん、何でもいいのですが、わたしにとって理想 的なコクヨの野帳を紹介します
- 野帳がいいのは:安い、表紙が厚い、紙がなかなかい い(裏映りしない)等々いろいろあります
- 最も素晴しいのは:薄いことです!
- 「一冊終わる」ことってとっても嬉しいことです
6.4 フィールドノーツの取りかた
- わたしの野帳(フィールドノート)をお見せし ます
- アドバイス: 余白をいっぱい取りましょう
- — 丁寧に書きましょう
- — その日のうちに書き足しましょう(色違いがよい)
- — 数日たってまた書くことも考えましょう(また違う色)
- — 消えない筆記具を使う!(わたしはジェル)




6.5 コンピューターの使い方
- (わたしの村に電気が来たのは 2008年ですが・・・)
- 大事なことをまず述べておきましょう
- プレインテキスト を使うこと(Proprietary なフォー マットのアプリを使わないこと)です
- 「入口は一つ」原則
- 「コンピューターの使い方」の フィールドワーク・ノーツ で説明しましょう
7 まだまだつづきます
- 第3講義 オーストラリアで博士論文を書く
- Back to Index
- Stand by Me (Slide Show 02:45)