博士論文を書く
1 はじめに
- オーストラリア国立大学へ行く
- 勉強の仕方
- あたまをかかえる
- あがったりさがったり
2 オーストラリア国立大学
2.1 フローレス島で
- フローレス島に行く前に(ジャカルタから)ANUの ジェームズ・フォックス教授(以後「ジム」)に手紙 を出したことは既に述べました
- フローレス島からも何回か文通を繰り返しました
- 2年たった時に「これでフィールドワークを終えて日 本に帰る」というメールを送りました
- 「帰る途中にANUに寄ってセミナーを開かないか?」 というお誘いを受けました
- わたし:「それもいいけど、どうせならそこで博士を取りたい な、どうだろう?」
- ジム:「いいね」
- というわけで、書類審査をとおり、オーストラリアの 国費留学生となりました
- とっても恵まれた条件でした
2.2 オーストラリア国立大学



2.3 おじさんの自慢話
- 留学は留学でいいのですが
- また(就職したあとでの)海外研修もいいのですが・・・
- 「学位」を取る留学は全く意味が違います
- ホンキンなのです(ウソンキンじゃなくって)
- 喜怒哀楽の日々なのです
- わたしの母校は「オーストラリア国立大学」です
3 勉強の仕方
3.1 読むべき本
- Fowler's Modern English Usage (link to Amazon)
- Punctuation についてはきちんと本で学びましょう
- イギリス方式とアメリカ方式と違います
- American: ``Yes,'' said he.
- British: `Yes', said he.
- わたしの愛読書は Sir Ernest Gowers の The Complete Plain Words (link to Amazon) です
- Style Manual はできれば手元に置いておきたいです
が・・・
- The Chicago Manual of Style (link to Amazon) はずいぶんと高いで す・・・
- とくに引用の仕方に関しては、きちんと把握してく ださい

3.2 十戒
- わたしがANUで博論を書いていた時、ティーコーナー の壁に「論文の書き方」が貼って ありました
- どうやら英米では有名なジョークらしいのですが、そ の歴史は知りません
- ウェブで調べてもいいのがヒットしませんでした
- 次のページのものは http://allowe.com/ から選択して取ったものです
- "Avoid overuse of 'quotation "marks."'"
- Also too, never, ever, ever be redundantly repetitive; don't use more words than necessary; it's highly superfluous.
- And don't start a sentence with a conjunction.
- Avoid commas, that are not necessary, and don't overuse exclamation marks!!!
- Be more or less specific.
- Bee careful two use the write homonym.
- Correct speling is esential.
- Beware of and eschew pompous prolixity, and avoid the utilization of enlarged words when shortened ones will suffice.
- Contractions aren't necessary and shouldn't be used.
- Don't be redundant; don't use more words than necessary; it's highly superfluous.
- Don't use no double negatives.
- Each pronoun agrees with their antecedent.
- Verbs has to agree with their antecedents.
- Eliminate commas, that are, not necessary. Parenthetical words however should be enclosed in commas.
- Eliminate quotations. As Ralph Waldo Emerson once said: "I hate quotations. Tell me what you know."
- Everyone should be careful to use a singular pronoun with singular nouns in their writing.
- Exaggeration is a billion times worse than understatement.
- Understatement is always the absolute best way to put forth earth-shaking ideas.
- Hyphenate between sy-llables and avoid un-necessary hyphens.
- If a dependent clause precedes an independent clause put a comma after the dependent clause.
- In all cases, you should never generalize.
- It is wrong to ever split an infinitive.
- Parenthetical remarks (however relevant) are (usually) unnecessary.
- Place pronouns as closely as possible, especially in long sentences, as of 10 or more words, to their antecedents.
- The de facto use of foreign phrases vis-a-vis plain English in your written tete-a-tetes is not apropros.
- The passive voice is to be avoided.
- Unqualified superlatives are the worst of all.
- Use delightful but irrelevant extra adjectives and adverbs with sparing and parsimonious infrequency, for they unnecessarily bloat your otherwise perfect sentence.
- Vary your words variously so as to use various words.
- Who needs rhetorical questions?
3.3 せんせいの使い方
- オーストラリアに行ってはじめて「指導」 (supervision) というのを受けました
- これがびっくり
- 懇切丁寧なのでびっくりしました
- オーストラリアの博士号のシステムは英国方式です
- 一日でも advisory board に所属したならば、その人 は examiner にはなれません
- 敵(examiner)と味方 (supervisor) がはっきりと分 かれます
- 博論の最終段階の指導はもっぱら敵を考えた指導とな りました
- 「ここは書くな、なぜなら Prof X はこういう議論は 嫌いだから」
- 「お前はこれこれの議論が好きじゃない のは知っている。しかし Prof Y はその議論がないと 不機嫌になる。ちゃんと書いておけ」
- 指導セッションでは何度も何度も書き直しをしました
- ジムが強調したのは Find the grain 「肌理を見つけろ」ということです
- これは EP の言葉だそうです
- EP (オックスフォード)は近代人類学の大先達です
- ジムは Rodney Needham の弟子、Needham は EP の弟 子です
- わたしは EP の曾孫弟子
- あなた方は EP の曾曾孫弟子になります
- 「肌理を見つけろ」を伝えたいと思います
3.4 本を読む
- 修士とは違う読み方をしなければなりません
- 博士論文はプロの第一歩です
- プロの眼で別のプロの論文を見ましょう
- 具体的に言えば、けなすのではなく・褒めるのです
- 「これだけ少ない民族誌的事実で、よくこんな論文を まとめられたなぁ」など(皮肉ではありません・我が 身を振り返りながらの感想です)
4 あたまをかかえる
4.1 フィールドノーツを読む
4.2 それなりに
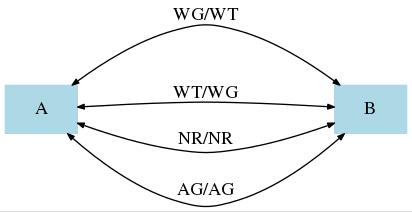
- それなりに書き進んではいたのですが、
- やはりどうしてもこの図にあるような状況を説明でき ませんでした
4.3 悲惨な青春
- みなでよく飲みにいきました
- その時に学んだ英語の諺です
- Misery loves company
- 閑話休題(それはさておき)・・・
- 英語の勉強法はわかりません
- Misery loves company の仲間で飲んでいるとき、女 の子と口喧嘩しました
- 彼女: ``XYZ is clever''
- わたし: ``No, he isn't!''
- たわいもない水掛け論をしていたのですが、彼女が
- ``Yes!'' といったので、「とうとう折れたか」とニ ンマリしました
- ・・・
- ま・どうでもいいですが、言いたいことは「口喧嘩す ると英語はうまくなる」かもしれないし
- 「酔っぱらうと英語はうまくなる」かもしれません
- そんなところにアメリカから博士をとったばかりの女 の子がやってきました
- その子がみんなに謎々をだしました
- How many Ph.D. students does it take to change a bulb?
- これは定型ジョークです
- Q: How many Irish (or whatever Ethnic) does it take to change a light bulb?
- A: It takes 10. One to hold the bulb and nine to rotate the ladder.
- さて、博論ジョークの答は
- It takes only one
- But it takes a looooooooooooooooong time

5 I See the Light!
- 生のフィールドノーツに戻りました
- 何冊も何冊も読みました
- んで・・・
- I See the Light! Blues Brothers (on Youtube)
- エンデで、知識はいろんな形伝達されます
- 父親やシンセキから知識を得ることもあれば
- もちろん経験から学ぶこともあります
- もっとも重要な知識は
- 「夜」(kombe)があなたに与える知識です
- kombe sodho (E) kobe nosi (L) と呼ばれます
- 夜があなたに知識を教えてくれるのです
- 「啓示」のようなものと言っていいでしょう
5.1 「道」から「象牙」へ
- 何度もフィールドノーツを読み返していくうちにある パターンがあるのが見えてきました
- そして決定的なのが MCCM(母方交差イトコ婚)に関 するあるイディオムの説明だったのです
- それは mburhu nduu wesa senda というエンデ語で す
- 一つの説明は次のようなものでした
- mburhu も wesa も「道」の意味である
- mburhu nduu wesa senda とは「道を辿り、路を結 ぶ」ということだ、と
- 「眼からうろこ」であるべきだったのです
- ここでは MCCM は「男の視点」ではなく、「女の視点」 から語られているのです
- 女は彼女の FZ の「道」を辿るのです
- 「EGO(女性)がFZ(おばさん)の道を辿る」
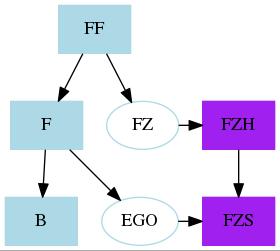
- さらにもう一つの説明がフィールドノーツにありまし た
- mburhu は「十」の意味、 wesa は「象牙」の意味 だというのです
- 「十」とは象牙を与えるときの(かつての)単位だっ たといいます
- すなわち mburhu nduu wesa senda は「象牙/婚資 を辿る」という意味なのだ、というのです
- EGO(女性)がFZ(おばさん)の道を辿るのではなく
- FZ のために払われた婚資の道を辿るのです
- 焦点は婚資に移ります
- EGO(女性)はFZ(おばさん)に支払われた婚資の道 を辿る
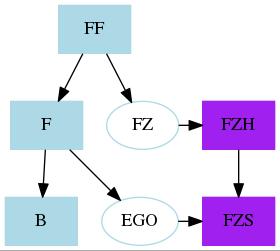
- 一度「親族」ではなく「交換」が重要だと気づくと
- フィールドノーツから次々に洞察を得ることができる ようになります
- (だから、「何でも書いておく」必要があるのです)
- たとえば wa'u se imu nai se imu 「一人降りて、 別の一人が上がってくる」というイディオムがありま した
- これは mburhu nduu wesa senda の別の説明です
- 家を基準に語られています
- ある家に生まれた女性が婚出します
- そのとき婚資がこの家にはいります
- その家の男性がその婚資を使って嫁を娶るとします
- 「一人上がって」きたわけです
- これこそが mburhu nduu wesa senda だというので す
- わたし(女性 EGO)が生まれてきたのは
- 父親が母親(M)と結婚したからである
- この結婚には婚資(象牙)が支払われている
- この象牙は、じつは、父の姉妹(FZ)が婚出したとき に受け取った婚資(象牙)である
- このような時、わたし(EGO)はもともとの婚資の出 所である FZH の息子 (FZS) と結婚するのだ
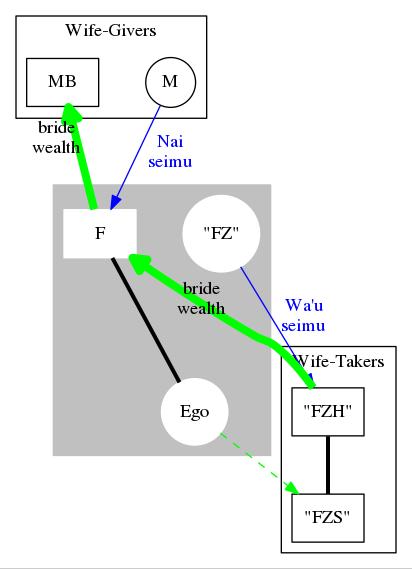
- まだまだ説明は続くのですがこのへんにしましょう
- ポイントは
- いままで親族関係の結婚(母方交差イトコ婚)だと思っ ていた結婚は、じつは婚資交換に基づく結婚だったの です
- ある親族関係にあるからある交換をするのではなく
- ある交換をしたから、ある親族関係にある、というこ となのです
- もう一度混沌の状態を見てみましょう
- 以下の図です
- ここで A から B に豚が与えられたとしましょう
- この時、 A は B に対して WG となるのです
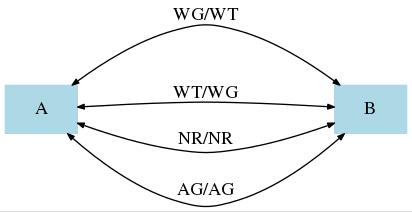
- WG だから豚を与えるのではなく
- 豚を与えたから WG となるのです
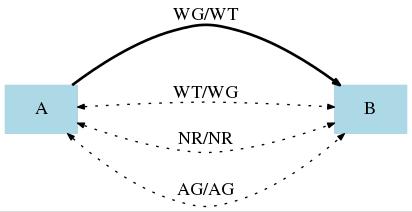
- WT は象牙を与えますが、同時に象牙を与えることが WT になることでもあるのです
- NR (「赤の他人」)は与えたり/受けとったりしません
- NR の例として「市場で出会う人」を挙げました
- NR は「売り買い」をするのです
- そして同時に「売り買い」をすることは NR になるこ とを意味します
- WG/WT は「与え/受け取る」
- AG/AG は「わかちあう」
- NR/NR は「売り買い」「取り替える」
5.2 知識を買うこと
- 親族関係が交換を作るのではなく、交換が親族関係を作るのです
- Friends make gifts; and gifts make friends (M. Mauss)
- じつは「鬱屈」の項で挙げた「お金」の話は、本来、 悩むべき話ではないのです
- 知識 orho mbe'o は与えられない
- なぜなら、その知識にはまだ与え手の「人格」が殘っ ているからだ
- そのような知識は「効果」 bhisa がない
- 知識は与え手から切り離されなければならない
- 日本の贈り物の例で説明(口頭)
- 日本の売り買いの例(口頭)
- だから知識は「買う」 mbeta 必要があるのだ
- わたしは誤解から「鬱屈」していたのだ
6 肌理を見つけた!
- それでは「与える」と「取り替える」はどう区別すれ ばいいのか
- 「宣言する」のです
- 「これを与える」 vs 「これを貸してやるから、いずれ何 かと取り替えろ」/「これを売るから、あとで代価を払え」
6.1 レッダあるいは豚の洗礼
- エピソード:「これは犬の肉だ」
- じつは豚肉だった
- 豚は WG が WT に与えるものです
- WT が WG に与えることは禁忌です
- でも WT の家に豚肉しかなかった場合
- レッダ(宣言)するのです、「これは犬だ」と
- ソンガという制度があります
- たいていは共同作業(種蒔きなど)に使うやりかたで
- さて・・・
- あるとき戦争がありました
- 海岸の村の人が山の村に攻めてきて、山の村では死人 も出ました
- 翌朝、海岸の村から魚売りがやってきました
- よく見ると昨日攻めてきたやつでした
- 彼を詰問すると
- 「だって、きのうは ソンガ だったから」
- 「きょうは魚売り として きたのだ」
6.2 肌理
- もっと一般化すると「宣言する」こと、それに基づい て「ふりをする」こと
- これがエンデの文化を理解するかなめなのです
- とうとう「肌理」を見つけたのです
- すでに述べた葬式などでも「宣言」が大活躍します
6.3 めでたしめでたし
7 これで最後です
まとめてみましょう
7.1 読む
- 修士の時:批判的に読む、何でも読む
- 博士の時:プロの眼で読む
- 何でも読む
7.2 書く
- 分かりやすく、簡潔に書く
- 形式を守る
- 何度も書き直す
7.3 調べる
- 丁寧に書く
- 何度も読む
- 何でも書く
7.4 考える
- 本を読んで、下書きを書いて、フィールドノーツを読 んで
- 頭をひねる( ひっくり返し論法 )
- その内に「夜がやってくる」でしょう