3 文化相対主義の不可能性
3.1 ピジョンホールとしての文化
3.2 語り得ぬものとしての異文化
3.3 ふつうの世界
4 能力 X を求めて
4.1 後半の戦略
4.2 独我論と自閉症
4.3 自閉症の世界
4.4 知覚的空想
Draft only ($Revision$ ($Date$)).
(C) Satoshi Nakagawa
Do not quote or cite without the author's
permission.
Comments are welcome
1年生の前期水曜1限に行なった授業を 思い出してほしい。 「5分間文化人類学入門」だ。 対象としての伝統社会(非西洋近代)、 方法としてのフィールドワーク、 そして理論としての「文化」という言葉の 多用だ。
この授業では、 水曜1限で取り上げなかった 「文化」について語りたい。
今年度(2016年)の授業は 「異文化の遊び方」と題する。 これは一昨年(「異文化の見つけ方」)と 去年(「引用と人生」)の続編である。
今年は(去年見つけた)不思議な現象、 一昨年の言葉を使えば「ためらいの時」に相当する 現象を見ていきたい。 具体的には芸術、観光、修辞などである。
一昨年(2014年)は文化相対主義を再生する、 という作業であった。
古き良き文化人類学の相対主義の 歴史について簡単に触れた。 それは人類学の魅力だったのだ。 ・・・・・ 【ミードなど】 ・・・・・
「概念枠組」あるいは 「概念図式」という語が、 この立場を代表する用語であろう。 ・・・・・ 【レンズなど】 ・・・・・
ところが、 その相対主義がピンチにたっているのだ。 危機は「異なる文化に住む人々を、われわれは理 解できない」というテーゼの形で示される(これを 「テーゼ2」 と呼ぼう)。 すなわちテーゼ1 から テーゼ2 が必然的に導かれるのではないかと いう非難が浴びせられているのだ。
もはやほとんどの(文化)人類学者は 「文化」という語を使わないですませるようにしている。 それは「文化相対主義」の苦境をじぶんで 背負い込まないためだ。 ・・・・・ 【】 ・・・・・ ・・・・・ 【工事中】 ・・・・・
わたしは「文化」という言葉を使いたい。 戦略はこうだ: まず最も直感的な(それゆえ最も脆弱な)文化の モデルから出発する。 そこからできるだけ精緻に議論をたてて、 そのモデルを、不可能性にまで追い込む。 その議論によって立った上で、 あらたな相対主義の可能性を打ち立てるのだ。 ・・・・・ 【工事中】 ・・・・・
講義の前半は文化相対主義を 不可能性にまで追い込むことに費やされる。
まず私の考える文化相対主義の中の 文化についてのイメージを与えよう。 文化は閉じて、完結していなければいけない。 別の言葉で言えば、 文化は「一つ、二つ」と 数えられるようなモノでなければならないのだ。 いささかの自己戯画化もほのめかしながら、 このような文化観に基づいた相対主義を 「ピジョンホール」と呼ぼう。
このピジョンホール相対主義の中に あらわれる古典的な文化が 成立するためのモデルは二つある: (1) コードモデルと (2) 水源地モデルである。
(1)コードモデルとは ・・・・・ 【工事中】 ・・・・・
(2) 水源地モデルは ・・・・・ 【工事中】 ・・・・・
【2016-10-12 はここから】
[野矢 2011]
・・・・・ 【デイヴィドソン】 ・・・・・ [デイヴィドソン 1991]
・・・・・ 【工事中】 ・・・・・ テーゼ2の言う「異文化が理解できない」よりも もっと致命的な結果が ・・・・・ 【工事中】 ・・・・・
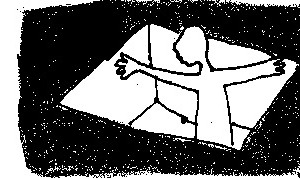
デイヴィドソンの議論が じつは(初期)ウィトゲンシュタインの 独我論 ( [Wittgenstein 1961]) と重なることを示したのが、 野矢である [野矢 2011] ・・・・・ 【工事中】 ・・・・・ しばらく野矢の議論を追っていこう。
・・・・・ 【ウィトゲンシュタインの独我論】 ・・・・・
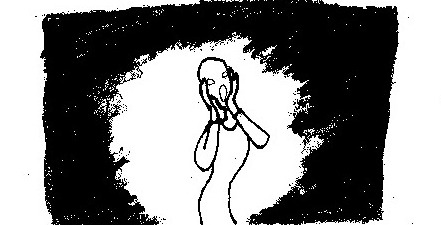
Now to the solipsistic world...
ここから後半である。
[村上 2008]
According to Murakami, [村上 2008] [Husserl 2005]
村上は自閉症児に欠けている能力として 「知覚的空想力」を挙げる。 わたしは一歩進んで、 自閉症に欠けている能力とは、 「知覚的空想力」だけなのだ、と言いたい。 すなわち、 能力Xとは、 「知覚的空想力」なのだ、と。
・・・・・ 【工事中】 ・・・・・ 自閉症児に欠けている能力はいくつも あるように見える。 しかし「知覚的空想力」はそれらの 能力に共通する能力だと、 わたしには思えるのだ。
【[2016-10-19]はここから】